当方的2023年展覧会ベスト10
年末なので、当方が今年見に行った463の展覧会の中から個人的に良かった展覧会を10選んでみました。例によって順不同です。
・「ラテンアメリカの民衆芸術」展(2023.3.9〜5.30、国立民族学博物館)



タイトルが如実に示しているように、ラテンアメリカ=中南米諸国において(アーティストに限らない)民衆たちが作った民芸品や、人々の社会運動の中で作られた作品などが並ぶ展覧会だったが、私たちが簡単に「民衆」と言って済ませてしまう諸存在の現在に至るまでの歴史的な形成過程にまで踏みこんだキュレーションがなされることで、中南米諸国において「民衆」という概念それ自体がいかに問題含みであるかも感得できるものとなっていた。一般論として、中南米諸国は独立後も国民国家の形成が上手くいっているとは言い難いものだが、そういう歴史の中で「民衆」もまた様々な定義が内的/外的に与えられ、そこにおいて様々な構想/抗争が現在においてもなお盛んである──そのことを出展物によって雄弁に語り切ってしまうところに、みんぱくの、ひいては民族学の底力を感じることができる良展覧会だったと言えるだろう。
・「Re: スタートライン 1963-1970/2023 現代美術の動向展にみる美術館とアーティストの共感関係」展(2023.4.28〜7.2、京都国立近代美術館)

1963年に東京国立近代美術館の分館としてオープンし、今年60周年を迎えた京都国立近代美術館が、開館当初の名物企画だった「現代美術の動向」展を現在において、当時の出展作品のみならず、史料なども広く渉猟して再考してみたといった趣の展覧会。現在の視点から見ると、「現代美術の動向」展が開催されていた1963年から1970年にかけての時期は、その間に68年革命を挟んでいることからも分かるように、前時代のモダンアートや前衛芸術から激変した時期とされているが、その激変の影響を真正面から受けながらも、なお前時代的なモダンアートの言説空間の中で紹介しようとしたこと──そしてそれが年を追うごとに困難になっていったこと──が、年ごとに区切られたコーナーの劈頭に(当時展示室前に掲げられていたであろう)挨拶文を再掲することで分かるようにしていたのは、ポイント高。当方もその文章を読みながら、く、苦しいねェ…… となったのだが、それはともかく、美術館が過去の企画を現在において批評的に「読み解く」系の展覧会としては、非常に出来の良いものとなっていた。
・ゲルハルト・リヒター展(2022.10.15〜2023.1.29、豊田市美術館)



ドイツの画家ゲルハルト・リヒター(1932〜)というと、様々なシリーズの絵画作品を手掛けることで、「絵画」という営みの現在を様々な観点から再考し続けていることで知られているが、東京国立近代美術館とこの豊田市美術館で昨年から今年にかけて開催された個展は、そんなリヒターの軌跡を大作群によって一挙に展望できる貴重な機会となった。卒寿記念 ゲルハルト・リヒター先生展←← リヒターについては既に様々な言説が紡がれており、この展覧会についても多くの言葉が費やされているので、詳細はそちらに譲るが、個人的にはこれがあの作品か〜となりながら見て回るだけでも相当良き経験になったし、彼の絵画観とドイツ現代史観が交錯した《ビルケナウ》に接することができたのが大きかった。
・「働く人びと 働くってなんだ? 日本戦後/現代の人間主義」展(2023.10.7〜12.17、神戸市立小磯記念美術館)
*出展作家:小磯良平、田中忠雄、内田巌、高山良策、新海覚雄、桂川寛、中村宏、大森啓助、須田寿、朝倉摂、脇田和、猪熊弦一郎、宮本三郎、中谷泰、北川民次、野見山暁治、真鍋博、梅宮馨四郎、海老原喜之助、靉嘔、尾田龍、西村功、菅原洸人、相笠昌義、やなぎみわ、澤田知子、会田誠、乙うたろう(前光太郎)


画題としての「労働(者)」「労働運動」を戦後日本の近現代美術はいかに主題としてきた/し損ねたかを、当時の作品を通して通観していくという展覧会だったが、そこに小磯良平(1903〜88)と彼の大作《働く人びと》(1953)を加えることで、事態をめぐる考察をより高解像度のもと立体的に組み立てており、この美術館にしては(←失礼!)クリティカル。当時であればプチブル(今ならさしずめ「実家が太い」になるだろうか)芸術家の一角を占めているとされていたであろう小磯のいかにもプチブルな人間主義に基づく労働観と、1950年代に大きな流れとなっていた「ルポルタージュ絵画」の作品群を並べることで、その双方を合わせ鏡として提示し、しかしかかる鏡像関係を破壊する〈出来事〉((C)アラン・バディウ)としての「68年革命」によって美術と労働&社会運動の関係が決定的に変質したことを現代に近い時代の作品を通して示しており、そういう意味では、2019年に兵庫県立美術館で開催された「Oh!マツリ☆ゴト 昭和・平成のヒーロー&ピーポー」展の続編というか批評的な応答となっていたと言えるだろう。かかる美術と労働の関係が変質した後における制作と労働とを(実際に神戸市内の小学校で図工の先生をしている)乙うたろう=前光太郎氏を通して見せていたのも、ポイント高。
・「泉茂 Newly Discovered Works」展(2023.9.13〜10.8、Yoshimi Arts & 2023.9.15〜10.8、the three konohana)



詳細はこちらを参照されたい。
数年前から泉茂(1922〜95)の画業を新たな位相において見せ直す作業を続けているYoshimi Artsとthe three konohanaだが、今回は近年新発見された泉の作品を見せるものとなっていた。話を聞いた当初は小品や習作の類だろうと思っていたのだが、実際は(なぜこれが泉の没後30年近くにわたって未発見だったのか理解に苦しむほどの)超大作だったので、まずそこに驚くばかり。Yoshimi Artsに出展されていたのは泉が多く手がけていた様式の集大成となる作品であり、the three konohanaに出展されていたのは、(終生作風を転換させ続けた泉にしては珍しくこれ一作しかないものであることから)ありえたかもしれない泉の姿を想像させるものであったのだが、いずれにしても、私たちは泉について未だほとんど何も知らないのではないかと思わせるほどインパクトの大きい展覧会であった。
・「走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代」展+「歴程美術協会からパンリアル、そしてパンリアル美術協会へ」展(2023.7.19〜9.24+2023.7.13〜10.1、京都国立近代美術館)



1963年に東京国立近代美術館の分館としてオープンし、今年60周年を迎えた京都国立近代美術館(←二回目)が、1948年に八木一夫たちによって結成された陶芸団体「走泥社」の歩みを、特にその前期(1973年ごろまで)に絞って見せていた。八木や走泥社に限らず、同時期の陶芸の動向──ほぼ同年に結成された「四耕会」や辻晉堂(1910〜81)との関係がクローズアップされることになるだろう──にも目配せをきかせることで、「前衛」精神が生まれ、発展し、頭打ちになるプロセス全体に通底する歴史性にも目を向けさせるものとなっていたのだが、かように前衛精神に至る流れを、歴程美術協会(1938〜43)の作品や同協会の参加者であった山崎隆(1916〜2004)の作品を紹介することで、戦前〜戦中にも敷衍させるという、企画展と常設展の連携プレイには舌を巻くことしきり。ええ勉強させてもらいました。
・「Paintings Now Redux──アジアの「いま」をめぐる」展(2023.9.1〜3、グランキューブ大阪3Fイベントホール(art stage OSAKA 2023内))
*出展作家:コラクリット・アルナーノンチャイ、ソピアップ・ピッチ、ブスイ・アジョウ、ホンサー・コッスワン、ロジト・ムルヤディ、ティン・リン、マリア・タニグチ、ルチカ・ウェイソン・シン、コア・ファム、ファディラ・カリム、マハラクシュミ・カンナパン
*ディレクター:遠藤水城



よくあるアートフェア形式から、複数名のディレクター/キュレーターを招いて複数のグループ展をひとつの会場内で同時多発的に開催するという形式に変わった今年のart stage OSAKA。そりゃこの方が良いですわな。わけても遠藤水城(1975〜)氏がディレクターとなって開催されたこの展覧会は、ASEAN諸国やインドにおける現代アートの一端を大作絵画という形で見せるものとなっており、普段あまり見かけない地域の作家たちのイキのいい仕事に接することができたという点で好感を持てるものとなっていたのだが、個人的にはこれらの地域が持つ、国民国家の形成というモーメントと脱国民国家的な後期資本主義への参加という相反するモーメントが複合的に進行している状況を「(絵画という)現場」として見せるという遠藤氏の企みにも注目しきり。2010年代以降、日本においてはアクティヴィズムやソーシャリーエンゲージドアートの類が戦後民主主義的な枠組を自明視することで急速に一国(平和)主義化していったのだが──酒井直樹氏の言う「引きこもりの国民主義」は、(ネット)右派に限った問題ではないのである──、遠藤氏の企みは出展作品や作家が直面している複合状況から背を向けている戦後民主主義に対するカウンターともなっていたと言えるだろう。
・中島麦「見えない色/みえる時間」展(2023.8.26〜9.11、KARINOMA 旧武石商店)



堺市にある築200年にもなる古民家を用いたKARINOMAなる施設で開催されたこの展覧会、今世紀初頭まで実際に人が住んでいたことから室内は各時代によって増改築と魔改造がされまくり、さらに一部は半壊していたので、さながら天然のコラージュ空間と化していたわけで、個人的にはそこにまず圧倒された。で、中島氏の作品はそんな超空間の各所にそっと置かれるように展示されており、影だらけでモノクロな室内空間と調和していて、なかなか良き。関西屈指のカラリストとしての地位を確立して久しい中島氏だが、このKARINOMAでは色彩の鮮やかさを見せつけるというより、超空間の中のワンポイントであることをむしろ積極的に選んでいるように見え、その控え目具合がむしろ心地良かったわけで。中島氏の色彩による陰翳礼讃は、思いのほか深い。
・田中佐弥「青い世界で蝶の夢を見る」展(2023.2.18〜3.1、Contemporary Art Gallery Zone)



関西を中心に、主にオブジェによって寓意・寓話を語る作品を作り続けている田中佐弥女史。今年はこの「青い世界で蝶の夢を見る」展と「現代暗黒寓話」展(2023.10.3〜8、KUNST ARZT)で個展に接する機会があったのだが、総合的な出来の良さという観点からすると、こちらを選びたい。モノによって迂回して語るというところに寓意の極意(極意?)があるのだが、意味や内容を直接的には語らなくても別の形で示すことが、展示空間全体を青くしてしまうという操作によってハイレベルで行なわれていたことに瞠目しきりだったわけで。田中女史は本職の占い師だそうで、ということは寓意や換喩という技法に関してはプロフェッショナルということになり、プロの達意を玩味できる貴重な機会となったのだった。
・宮岡俊夫「僕の父親 内なるアメリカ」展(2023.11.25〜12.3、KUNST ARZT)


詳細はこちらを参照されたい。
以前の個展で昭和天皇を描いて天皇アート((C)アライ=ヒロユキ)界隈に名乗りをあげた宮岡氏だったが、今回は近衛文麿を描き、そこに歴史的な含意を──史実一辺倒にならない形で──含みこませることで、天皇を直接的に描くよりもはるかに高いレベルの天皇アートをものしていたことに驚かされるばかり。そうした宮岡氏の企みによって、私たちは戦後民主主義のもとに何を不可視化して忘却したかを改めて想起することになるわけで、戦後日本/戦後民主主義に対する実践的批評として、小規模ながらきわめてクリティカルであった。
当方的2022年展覧会ベスト10
年末なので、当方が今年見に行った484の展覧会の中から、個人的に良かった展覧会を10選んでみました。例によって順不同です。
・「ミニマル/コンセプチュアル ドロテ&コンラート・フィッシャーと1960-70年代美術」展(2022.1.22〜3.13、愛知県立美術館)
*出展作家:カール・アンドレ、ダン・フレイヴィン、ソル・ルウィット、ベルント&ヒラ・ベッヒャー、ハンネ・ダルボーフェン、河原温、ロバート・ライマン、ゲルハルト・リヒター、ブリンキー・パレルモ、ダニエル・ビュレン、リチャード・アートシュワーガー、マルセル・ブロータース、ローター・バウムガルテン、リチャード・ロング、スタンリー・ブラウン、ヤン・ディベッツ、ブルース・ナウマン、ギルバート&ジョージ(ギルバート・ブロッシュ+ジョージ・パサモア)


1960年代から70年代にかけて主にアメリカで大きなムーヴメントとなったミニマルアートやコンセプチュアルアートだが、それをほぼ同時期にヨーロッパに紹介する役割を果たしたギャラリストのドロテ・フィッシャーとコンラート・フィッシャー夫妻に焦点を当てた展覧会。作品のみならず資料も豊富に展示することで、これらのムーヴメントの単なる紹介者にとどまらない重要な伴走者としてフィッシャー夫妻(と、彼/彼女が画廊を構えたデュッセルドルフという場所)の特異性を改めて浮き彫りにしており、ある意味見慣れた作品群に対する解像度を上げつつ別の側面にも開いてみせていたのは、普通にポイント高。
・庵野秀明展(2022.4.16〜6.19、あべのハルカス美術館)


『新世紀エヴァンゲリオン』や『シン・ゴジラ』etc.といった作品の監督として、アニメや特撮といったジャンルにおいて圧倒的な存在感を見せ続けている庵野秀明(1960〜)氏という異能存在を軸にして、戦後日本の文化史の一断面を極端な形で見せるという意欲的な展覧会。庵野氏のライフヒストリーを追う中で氏が接してきた(であろう)文物たちと氏が作ってきた映像作品などをとりあえず並べて見せるという構成はベタではあるのだが、その人自身の人生があるジャンルやカルチャーの消長と端的に一致しているかのように見えてくるところに庵野氏の魅力と怖さがある──その意味で氏の存在は映画における淀川長治(1909〜98)やジャズにおけるマイルス・デイヴィス(1926〜91)と比せられるかもしれない──のだが、その現在をシャープに提示する試みとしてなかなかよくできていた。
・「没後50年 吉原治良の小宇宙」展(2022.7.30〜12.18、兵庫県立美術館)


今年は吉原治良(1905〜72)の没後50年ということで、彼が総帥として君臨した具体美術協会についても、彼のもとに参集した作家の個展も含めて盛んに展覧会が開催されていたのだが、その中でも最近兵庫県立美術館に寄贈されたという下描きやドローイングなどからなるこの展覧会は「小宇宙」というタイトルにふさわしい小品中心の構成ながら、吉原のあまり見えてこなかった側面に光を当てるものとなっていた。ことに具体結成前夜の昭和20年代に描かれたドローイングは、その前後の作品にない洒脱さがあって、個人的に驚き。半年近い会期が設定されていたことで、岡本太郎展(2022.7.23〜10.2、大阪中之島美術館)や「すべて未知の世界へ──GUTAI 分化と統合」展(2022.10.23〜2023.1.9、国立国際美術館・大阪中之島美術館)、さらには李禹煥展(2022.12.13〜2023.2.12、兵庫県立美術館)とも並べて見る機会があったことも重要。特に岡本太郎との関係は(二人が一時期同じ二科会にいたこともあって)、今後の研究や批評が待たれるところ。いつぞやの「小磯良平と吉原治良」展(2018.3.24〜5.27、兵庫県立美術館)のように企画展に結実すれば良いのだが。
・「BACK TO 1972 50年前の現代美術へ」展(2022.10.8〜12.11、西宮市大谷記念美術館)


西宮市大谷記念美術館が開館したのが1972年ということで、その1972年に制作された作品や当時の記録写真などを集めて1972年の日本・現代・美術界隈の状況を見せ直すという、ありそうでなかなかなかった好企画。1972年は吉原治良の急逝によって具体美術協会が解散したことで関西では激震が走った年として記憶されているのだが(同展では、その具体がオランダで開催しようとしていたアートフェス関連の資料や吉原の絶筆が展示されていた)、そのことにとどまらない様々な新しい動きも勃興していた──ことに京都市美術館で開催された京都ビエンナーレは、〈もの派〉や〈日本概念派〉の梁山泊状態だったことが、残された記録写真からも窺い知ることができる──ことにもきめ細かく目配せが効いており、個人的には勉強になった。特にこの時期の版画作品が多く展示されていたのは、「かつて版画ブームというものがあったらしい」という形でしかこのジャンルに接することしかできなかった者としては、視野の欠落を認識させて補うにあまりあり、眼福。
・「生誕100年 清水九兵衞/六兵衞」展(2022.7.30〜9.25、京都国立近代美術館)



京焼の大名跡である清水六兵衞の名を継いだ七代清水六兵衞(1922〜2006)は1970年代以降清水九兵衛と名乗って金属による立体作品を多く手掛けることになるが、その双方にまたがった回顧展となったこの展覧会は、陶芸と彫刻→立体、工芸とファインアートの双方に引き裂かれながら屹立する、依然として問題含みな存在としての清水九兵衞/六兵衞の仕事を提示する良い機会となっていた。ことに近年それまで工芸に属するとされてきた諸ジャンルがそのままでファインアート扱いされることが増えており、そのような動きによってチャージされた創造性が最も開花しているのが(現代)陶芸なのだが、その現代陶芸と立体とにわたって展開していった清水九兵衞/六兵衞の創作の軌跡は、かかる工芸/ファインアートの関係性が変貌する前夜において双方にまたがって活動することの困難や戦略性(〈affinity〉(親和)は、その戦略の一端を示している)を垣間見せるものとなっており、一見すると工芸vsファインアートという問題構制が雲散霧消したかに見える現在において、逆にアクチュアルであると言えるだろう。
・松平莉奈「聖母子」展(2022.2.5〜7、大阪カテドラル聖マリア大聖堂)

詳細はこちらを参照されたいが、アートと宗教性ないし信仰との関係性という古くてなお新しい問題構制に対してそのような切り口があったかと瞠目したもので。もとは長崎県にある天祐寺からの依頼で描かれたそうだが、禁教令下においても信仰を守り続けたキリシタンたちが聖母と観音菩薩とを同一線上に見出したことから出発して、特定の宗教に還元されない原初の聖性を描き出すという試みがこのような作品に結実し、さらに大阪におけるカトリック信仰の中心地である大阪カテドラル聖マリア大聖堂に展示されたことの意義は大きいと言わなければならないだろう。で、そこに松平女史が近年精力的に行なっている「「日本画」を歴史に再び着地させようとする試み」が重ねられていることにも要注目。ところでこの聖堂には堂本印象(1891〜1975)が描いた、聖母子にかしずく高山右近と細川ガラシャが描かれた巨大な絵画があるのだが、そんな作品と対峙するように置かれてちゃんと拮抗・均衡しえていたわけで、松平女史のマスターピースにこのような形で接することができたのも、個人的に意義深かった。
・オノユウコ「GARDEN」展(2022.5.27〜6.7、アトリエ三月)



アートと宗教性ないし信仰との関係性という古くてなお新しい問題構制に対してそのような切り口があったかと瞠目したもので(二回目)。一見してわかるように、異世界における異教の教会絵画といった趣を見る側に抱かせるような作品なのだが、中世におけるカトリック的な、そのカトリックによって早くに異端とされた東方の初期キリスト教的な、ゾロアスター教のような古代オリエントの諸宗教的な……──といった雑多な図像が渾然となっていたわけで、このシンクレティズムぶりをそのままキャラクターアートの文脈に持ち込んで提示するという力技(そう、これはまさに力技と呼ぶにふさわしい行為なのである)には本当に驚かされた次第。信仰を架空の宗教に仮託するという行為自体はありふれているし、現在ではそれは「中二病」「厨二病」と呼ばれていたりもするものだが、そのような行為を突き詰めつつしかしシンクレティズムとキャラクターアートに落としこんで見せるところに、オノ女史の慧眼と信仰心的な切迫感とが同時に現われており、スリリングな鑑賞体験となったのだった。
・「わたしはメモリー」展(2022.12.15〜25、京都市美術館 別館)
*出展作家:秦野良夫、小原美鶴、似里力、西澤彰、三原厳、森川大輔、小幡正雄
*キュレーター:寺岡海(art space co-jin)



近年、京都や大阪ではいわゆる「障害者アート」を、「障害者」をカッコに括った「アート」として(再)提示する試みが散発的に出てきており、それは従前の「アール・ブリュット」や「アウトサイダー・アート」といったフレームと違った視点から見直すことを鑑賞者に要請するものとなっているのだが、京都においてこういった試みの一翼を担っている様子のart space co-jinの企画によるこの展覧会は、出展している障害者たちのライフヒストリーやバックグラウンドなども込みで見せることで、「障害者」をカッコに括った「アート」として提示していたわけで、現時点における「障害者アート」を見直す試みのひとつの良き達成となっていた。ことに聴覚障害者として生き、60歳を過ぎてから自身の人生経験を描くようになった三原巌(1932〜2021)の作品に瞠目。ある障害者の戦前〜戦中〜戦後が描かれていたことで、「わたしはメモリー」という展覧会タイトルを端的に象徴していたし、戦時中、聴覚障害者は手話を禁じられていたことを、彼の作品によって初めて知ったのだった。
・tsubasa.「TSUBASAISM」展&「ONE OF EACH」展(2022.3.18〜4.3、アトリエ三月)
*「ONE OF EACH」展出展作家:tsubasa.、maaco、HARUN、中島麦、女と男 ワダちゃん、四星球 まさやん、儀間建太、トミタ栞



関西のあちこちでライヴペインティングを行なうことでキャリアを積んできたtsubasa.氏。「TSUBASAISM」展はそんな氏の新作絵画が、「ONE OF EACH」展は氏の画業10周年記念ということで知人たちに声をかけて作品を作ってもらったトリビュート展だった。タブローにおける今後の飛躍にさらに期待が持てるものとなっていた「TSUBASAISM」展はもちろん、「ONE OF EACH」展の出来の良さに驚くことしきり。アーティストのみならず俳優やバンドマン、果ては吉本所属の芸人まで出展していたわけで、tsubasa.氏の交友関係の広さもさることながら、大阪における文化的な基底現実とその現在とを、アートに限らない形で提示するものとなっており、氏がどこまで意識的だったかは分からないものの、キュレーションとして非常に上手かった。本職の(?)キュレーターもこのくらいできないといけない。いずれにしても、この展覧会に接してからだと「関西の80年代」展(2022.6.18〜8.21、兵庫県立美術館)もさらに解像度を高めた状態で接することができたわけで。
・林真衣展(2022.11.7〜12、Oギャラリーeyes)



以前から昭和時代の住宅にまま見られた型板ガラスを通して見た/反射した光(景)を描き続けている林真衣女史。窓ガラスとそこに映ったこちら側と向こう側を描くという態度によって画面における光のありようは複雑になり、その複雑さを抽象画として描くところに林女史の眼目があるのだが、そこに様々な紋様が施された型板ガラスのレイヤーが加わることで、抽象画でもあるとともに紋様が持つデザインによって絵画史やデザイン史に不意にアクセスされることになるわけで、そのあたりに特筆大書すべき美質があると言えるだろう。今回の場合、油絵具を薄めに溶いて描くことで画面にさらに別の薄い物質性が加わることで画面はさらに渾然となり、しかし単純なカオスにならないで抽象画として成立しており、そういうところに林女史の実力のほどがうかがえる。
松平莉奈《聖母子》について
森ノ宮にある大阪カテドラル聖マリア大聖堂(以下、玉造教会)で2月5〜7日の三日間だけ開催された松平莉奈女史の新作《聖母子》の展覧会を見てきました。京都を中心に、新世代の日本画家の一人として個展やグループ展──とりわけ同世代の日本画家たちによるユニット「景聴園」での活動が際立っていることは、ここで特筆されるべきでしょう──様々な形で活動している松平莉奈(1989〜)女史ですが、大阪での個展は管見の限り初めてでして。当方は初日の午前中に見に行きまして、松平女史と歓談しながら作品に接することができました。記して感謝申し上げます。
さておき、今回の《聖母子》、そのタイトルから一見即解なように、聖母マリアが幼いイエス・キリストを抱いているという、西洋絵画ではあまりにもおなじみの画題が、教会の祭壇画に非常によく見られる三幅対の形式で描かれています。真ん中に聖母子、左側に花鳥、右側に現代人の衆生たちが描かれており、古典的な画題の中に現代人を登場させつつ違和感なく構成して見せる松平女史お得意の画風がいかんなく発揮されているのですが、しかしこの絵において最も異彩を放っているのは、その聖母マリアが仏像のような相貌をもって描かれていることである。もともとこの《聖母子》は、長崎県諫早市にあるという天祐寺なる寺院からの依頼で描いたものだそうで、この展覧会のあとほどなくして同寺の所蔵となるとのこと。仏教寺院からの依頼で描かれた作品がいかなる経緯で今回大阪におけるカトリックの中心である(らしい)玉造教会にて展示されることになったのかは詳しくは分かりませんが、シンクレティズムの相貌をともなって描かれた《聖母子》がほかならぬカトリック教会で展示されたことの意義はきわめて大きいと言わなければならないでしょう。玉造教会には堂本印象(1891〜1975)が描いた巨大な聖母子像──和服姿の聖母子に(同教会が顕彰している)細川ガラシャと高山右近がかしづいているというもの──があることで知られているそうですが、広い礼拝堂の入口付近に置かれた《聖母子》は、そんな堂本の筆による聖母子像とサイズの大小こそ違え対峙する形になっていたわけで、これはここで見てこそ真価を発揮する作品だなぁと思うことしきりでしたし、松平女史の画業について見ていく上でも、今後マスターピースになるのではないでしょうか。
──いささか先走り過ぎたので、もう少し細かく見ていきましょう。今回の依頼主である天祐寺の住職氏はこの《聖母子》を発案した契機について次のように述べている。
もしもヨーロッパ、もしくは日本で仏教が禁止さてて[←ママ]いたならば、おそらく仏教徒は聖母を観音菩薩として拝んだであろうという仮定から始まりました。
つまり《聖母子》においては聖母マリアは観音菩薩の姿を取って描かれていることになるわけですが、このことは、禁教令が敷かれていた江戸時代において隠れキリシタンたちが観音像の形をした聖母像──いわゆる「マリア観音」──を礼拝することで信仰を維持したという、日本史の教科書にも書かれているエピソードを思い起こさせます。もっとも、かかる教科書的な「マリア観音」という言い方は明らかに非信者目線での言い方であるのもまた事実ではあり、そのような教科書的な言い方から離れて、聖母マリアと観音菩薩を同列に見出した隠れキリシタンたちの行為を仏教/キリスト教双方の信者目線で改めて主題化し、そこに信仰心を再-賦活しようという試みが天祐寺側にあったことは、ここで強調されるべきでしょう。したがって、「マリア観音」には、聖母マリアを観音菩薩の中に見出すという精神的なベクトルと、逆に観音菩薩の中に聖母マリアを見出すという精神的なベクトルが同時に存在していることになります(仏教において、観音菩薩は(男性/女性のような)様々な対立を越えた存在として定義されることが多いと言われています)。この二重の運動によって「聖母像、観音像に通底する原初の聖性」が見出され、それが絵として現働化しているのが、この《聖母子》であるわけです。そしてさらに、近世以降の長崎という場における宗教的な風土がさらなるレイヤーとして重ねられる──近世の長崎では仏教徒と隠れキリシタンは意外と混住しており、時として仏教寺院が隠れキリシタンを保護する場面もあったという。そのような歴史的な記憶にも見る側を使嗾させつつ、この絵は存在している。
以上のように、《聖母子》は観音菩薩の姿を取って聖母マリアを描くことで、宗教性あるいは諸宗教「に通底する原初の聖性」を絵において/絵によって遡及的に構成していくことが企図されているわけですが、ところで松平女史においてかかる「絵において/絵によって遡及的に構成していくこと」は、彼女における〈日本画〉というジャンル自体の問題としてもあることに注目する必要があります。画家であり、近年「パープルーム」という運動体を率いていることでも知られている梅津庸一氏は彼女(や「景聴園」)の活動について《日本画の起源を求めて歴史の古層にタッチするような試みであり、日本画を超えて東洋画のコアににじり寄ろうとしているように映る》と述べていますが*2、〈日本画〉というジャンルそれ自体の制度性──明治時代(特に日露戦争以後)において、前近代にあった諸流派から相対的に断絶したものとして、とりわけ欧米から導入された油絵との対比において想像/創造されたものであることが論じられて久しい現在、松平女史の試みは、そうして想像/創造された〈日本画〉をもう一度歴史に着地させようという試みとして記述することができる。松平女史は制作活動の傍ら、江戸時代における様々な流派の粉本を模写するという活動を続けています(その活動の成果は一昨年の個展「うつしのならひ」展*3に結実している)が、模写という行為を通して、さらに言うと描くことと思考することが一致するように模写を行なうことで、「歴史の古層にタッチ」しようとしていると言えるでしょう。
《聖母子》においてなされているのは、諸宗教に通底する原初の聖性を絵において/絵によって遡及的に構成していくことのみならず、前近代からの断絶として始まった〈日本画〉を「歴史の古層にタッチする」=歴史に再び着地させようとする試みであり、そして今回の場合、宗教画という相貌をまとうことで、画題の趣味嗜好を超えたアクチュアリティを帯びている。この作品が松平女史のマスターピースになるであろうというのは、かような位相においてなのです。
当方的2021年展覧会ベスト10
年末なので、当方が今年見に行った402の展覧会の中から、個人的に良かった展覧会を10選んでみました。例によって順不同です。
・HUB IBARAKI ART PROJECT 2021作品発表 黒田健太「今、ここで、立ち尽くすために -now, here, nowhere-」(2021.9.26 茨木市福祉文化会館)
*選出作家:黒田健太
*チーフディレクター:山中俊広

詳細はこちらを参照されたいが、今回の選出作家である黒田健太(1995〜)氏が茨木市の街中でセッションしたストリートミュージシャンやダンサーと協働して舞台を作っていく──というプロセスから想像されるようなありきたりさから、ダンサーとしての身振り=思考のメタファーとしてのダンス((C)アラン・バディウ)によって極限まで遠ざかっていった舞台作品となっていたわけで、「「アート」と「公共性」」という非常にありふれたテーマに対する介入・批評(そう、これは作品という形態を取った批評でもあったのである)としてブリリアントであったと言わなければならないだろう。それにしてもかような作品を輩出したHUB IBARAKI ART PROJECTが来年以降誰を選出しどのようなプロジェクトを展開していくことになるのか、黒田氏によってハードルが異常に高くなった感があるだけに、ますます気になるところではある。
・「No Man’s Land──陶芸の未来、未だ見ぬ地平の先」展(2021.3.20〜5.30 兵庫陶芸美術館)
*出展作家:秋永邦洋、稲崎栄利子、かのうたかお、木野智史、金理有、谷穹、出和絵理、新里明士、林茂樹、増田敏也、松村淳、見附正康、山村幸則、若杉聖子、度會保浩



関西と東海・北陸で主に活動している若手〜中堅陶芸家を集めたグループ展といった趣だったこの展覧会。「No Man’s Land」というタイトルの含意以上に、ゼロ年代に活動を始めた作家を集めることによって、陶芸版平成美術展として(地域的な偏りはあるものの)意外と出来の良い展覧会となっていた。一般論として、工芸諸分野においてはゼロ年代から2010年代にかけて創作と受容、ファインアートとの関係の取り方をめぐる体制や作法などから作者が次第に自由になっていったのだが、とりわけ陶芸はこの間若手が活発にムーヴメントを牽引し(イケ⭐︎ヤンやへうげ十作など)、さらに──織部焼で今日にも名を残す古田織部(1543〜1615)を主人公にした山田芳裕氏のマンガ『へうげもの』のスマッシュヒットもあって──現在における若手の実践が歴史や伝統と地続きであることが狭い界隈を越えて可視化されたもので。そういった動きによってチャージされた現代陶芸の多様性と多産性を一望できる貴重な機会となったのだった。
・「堀尾昭子の現在」展(2021.9.19〜12.5 西脇市岡之山美術館)

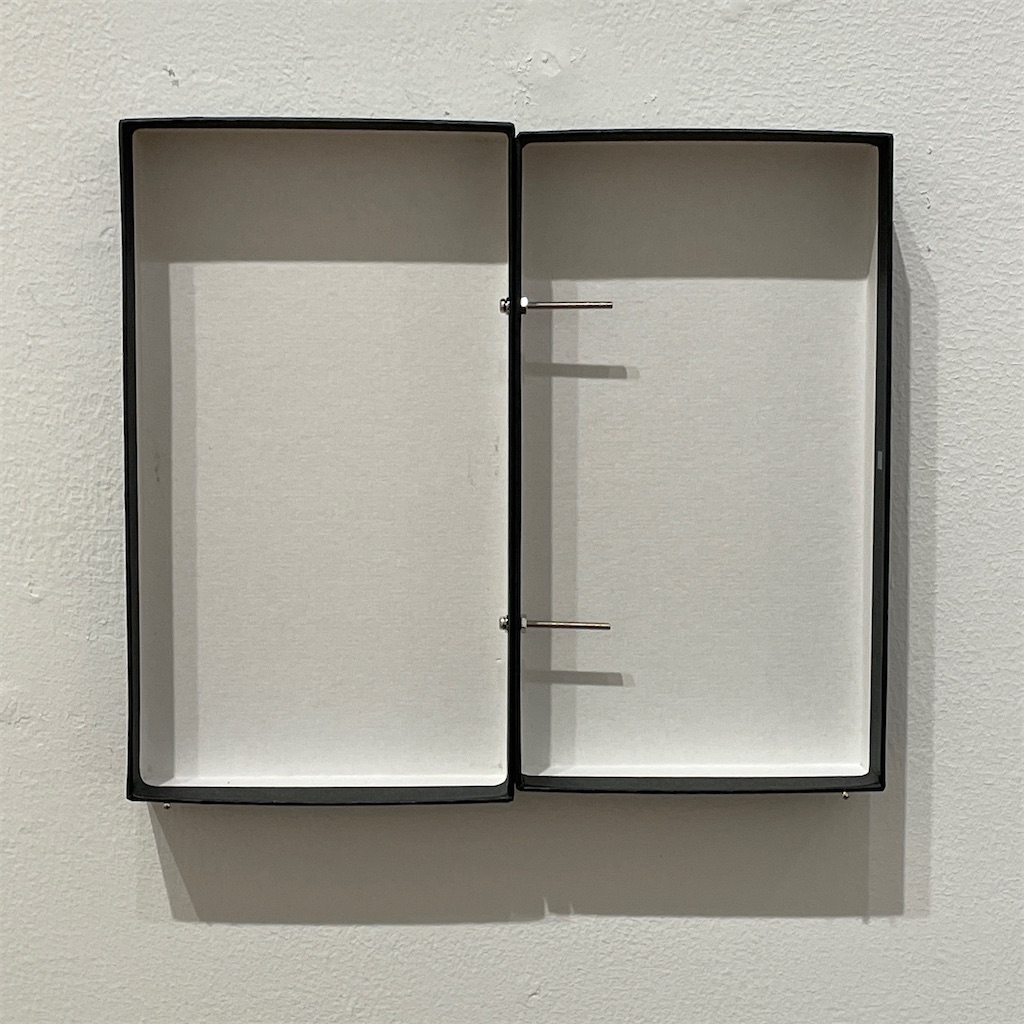
後期の具体美術協会に参加し、現在に至るまで半世紀以上にわたって創作活動を続けている堀尾昭子(1937〜)御大。この展覧会ではそんな御大がここ二、三年に制作した作品が数十点並んでいた。いずれも紙や木、アクリル、鏡などを素材とした極小のオブジェで、ムダを極限まで削ぎ落としたソリッドなものとなっており、極小ながらも見応えは無限にあるわけで。堀尾御大が美術家として世に出た頃はミニマルアートの勃興期に当たり、その後ミニマリズムやポストミニマリズムといった諸潮流が現代美術においてひとつのトレンドをなしていくのだが、御大の作品はそれらと並行しているような相貌を見せながらも、しかし微妙なズレをともなったものとしてあり続けてきたし、現在もそうであることが一見即解であった。最終日になんとか時間を作って見に行って大正解。
・「フェミニズムズ」展&「ぎこちない会話への対応策 第三波フェミニズムの視点で」展(2021.10.16〜2022.3.13 金沢21世紀美術館)
*「フェミニズムズ」展出展作家
青木千絵、遠藤麻衣、遠藤麻衣×百瀬文、風間サチコ、木村了子、森栄喜、西山美なコ、碓井ゆい、ユゥキユキ
*「ぎこちない会話への対応策 第三波フェミニズムの視点で」展出展作家
岩根愛、木村友紀、小林耕平、さとうりさ、ミヨ・スティーブンス-ガンダーラ、長島有里枝、潘逸舟、藤岡亜弥、ミヤギフトシ、渡辺豪



詳細はこちらを参照されたいが、もともとひとつの展覧会として企画されていたのが紆余曲折あって二本立てとなったそうで、どういう形であれ開催にまで辿り着けたのは、金沢21世紀美術館の館長が女性(長谷川祐子女史)だからか。それはともかく「フェミニズムズ」展においてはいわゆる〈第三波フェミニズム〉以後の現代日本におけるアート/フェミニズムの多様性と多産性を体現した作家と作品が、「ぎこちない会話への対応策」展ではその〈第三波フェミニズム〉の勃興期〜展開期における社会-文化運動論的な文脈と交差させられるような作家と作品が並んでおり、アート/フェミニズムを同時性と歴史性という形で複眼的に見ることができるように構成されていたのは、かかる紆余曲折の思わぬ副産物であったと言えるかもしれない。かかる同時性と歴史性によって、欧米のムーヴメントのカーボンコピーではない日本のフェミニズム史の可能性が(多くのフェミニストが未だに否認している中で)示されたことは後々効いてくるだろう。
・「It’s a small world 帝国の祭典と人間の展示」展(2021.2.6〜28 京都伝統産業ミュージアム)
*キュレーター:小原真史

1905年に大阪で開催された第五回内国勧業博覧会において、アイヌ民族や沖縄県人、台湾や東南アジアなどの先住民族が「展示」されて物議を醸したという「人類館事件」については、文化人類学や民族学界隈においてときおり俎上に乗せられているようであるが、この展覧会では小原氏が近年発見したという、その人類館において「展示」されていた人々の集合写真を軸に、氏が収集してきた19世紀以来の万博や世界各地の博覧会で発売されていた絵ハガキやポスターなどを加えて、「人間の展示」が当時植民地主義・帝国主義の正当化のために広く行なわれていたことを示す展覧会となっていた。それを(京都での内国勧業博覧会のために整備された)岡崎公園内にある施設で行なうというのは、なかなかポイント高。特に第三共和制時代のフランスが万博を植民地主義の正当化のために大いに「活用」したのだが、そこではフランス革命以来の同国のレゾン・デタであった自由・平等・博愛や人権思想がそのまま帝国主義のイデオロギーとなっていたわけで、そこにも目配せを効かせた大量の史料によって「人類館事件」が特殊日本的なものにとどまらない問題を孕んでいることを見せるものとなっていたことも特筆すべきだろう。
・「編集者 宮内嘉久──建築ジャーナリズムの戦後と廃墟からの想像力」展(2021.3.22〜5.1*1 京都工芸繊維大学美術工芸資料館)

『新建築』誌の編集者として出発し、その後フリーとなって多くの建築書を手がけた宮内嘉久(1926〜2009)。その彼が書籍編集の傍ら、1970〜79年(と2002〜2005年)に発行していたミニコミ誌「廃墟から」に注目した展覧会。この「廃墟から」は建築のことに限らず、論説や身辺雑記、彼が当時読んでいた様々な分野の本からの引用などと内容が多岐にわたっており、今風に言うとブログやオウンドメディアといった相貌を見せているのだが、会場で実際にいくつかの号を読んでみると「建築」と「建築批評」から「(来るべき)建築運動」を展望するためのアジテーションといった趣が強かった。現在の視点から見ると時代的な限界も当然あるのだが、宮内においては、来るべき建築運動を〈68年革命〉に使嗾されつつしかし「廃墟」というイメージから語らざるを得なかったという矛盾は、現在においてこそ全く解決されていないものとして正面から見据えられなければならないだろう。来るべき建築運動もおそらくどこかで目指していたであろう市民=国民という等式が崩壊して久しい状況(現在の戦後民主主義=リベラルが否認し続けているのは、端的にかかる状況である)においては、特にそうである──そのようなことを考えさせられる。
・「二つの時代の平面・絵画表現 泉茂と6名の現代作家展」(2021.10.9〜31 Yoshimi Arts, the three konohana)
*出展作家:泉茂、今井俊介、上田良、加藤巧、佐藤克久、杉山卓朗、五月女哲平



詳細はこちらを参照されたいが、関西の美術館の常設展でだいたい一、二点展示されている(が、それ以上でもそれ以下でもない)前時代の画家というイメージが長年定着していた泉茂(1922〜95)の作品に対する解像度を高めていく試みをここ数年継続的に行なっていたYoshimi Artsとthe three konohanaが、周りの作家──それも、世代的に泉との同時代性や時代背景をほとんど共有していないような──を引き入れることで、ついに同時代の、現存作家としての泉茂という相貌を与えるに至ったことに、最初期からずっと両ギャラリーの試みを注視してきた者としては感慨深かった。「二つの時代」と銘打ってはいるものの、そこにあるのは紛れもなくひとつの平面・絵画精神であり、そのような「ひとつ」を圧倒的な理解力とクオリティで現出させた六人の出展作家の仕事には、当方も非常に勉強になったわけで。
・ミケル・バルセロ展(2021.3.20〜5.30*2 国立国際美術館)

スペインの画家ミケル・バルセロ(1957〜)の、日本では初とな美術館での個展として開催されたこの展覧会。当方は彼のことを全く知らないで作品に接する形となったのだが、大画面に大量の絵具(や様々なメディウム)をぶちまけるパワープレイな絵画でありながら、随所に絵としてまとめ上げるセンスの良さ──それは、マリ共和国に構えたアトリエで現地の人々を描いたドローイングや、油絵具で塗りつぶされたカンヴァスに強酸性の液体でササっと描いたポートレートにおいてとりわけ際立っていた──が垣間見え、土着的で初期衝動が全開なプリミティヴィズム系の絵画が苦手な者でも「見られる」ものとなっていたことに驚くことしきり。同じプリミティヴィズムを志向していても日本人はおそらく彼のように描くことはできないのではないか。その意味で世界にはまだ見ぬ強豪がたくさんいるものだと瞠目させられた。
・「TANKING MACHINE REBIRTH 90年代のヤノベケンジ」展(2021.5.29〜7.19 MtK Contemporary Art)


ヤノベケンジ(1965〜)氏というと、1970年の大阪万博の体験とサブカルチャーの記憶などを重ねてみせた特異なオブジェ作品で関西の現代美術界隈にデビューしたことで知られるが、そんなヤノベ氏の90年代の仕事の中でも特筆大書すべきものとなっている《TANKING MACHINE》の再制作と、自作のガイガーカウンターつき防護服でチェルノブイリを訪問する《アトムスーツプロジェクト》&そこから派生した諸作品の再展示からなるこの展覧会。個人的にはゼロ年代初頭、まだ万博公園にあった頃の国立国際美術館でこれらの作品には接したことがあるのだが、現在の視点から見たとき《アトムスーツプロジェクト》が全く別様の相貌をもって現われたことに驚くことしきり。個人的な記憶と切迫感だけでもってチェルノブイリを訪ねるところまで行き着いたヤノベ氏のようには、おそらく現在の日本においてはできないだろうと思わされた──現在では、何らかの批評理念(「ダークツーリズム」とか)や政治的・倫理的正しさに「エンゲージ」した形跡を介在させないと、間違いなく炎上案件になってしまうから──わけで、この少し前に近くの京都市美術館で開催されていた「平成美術」展(2021.1.23〜4.11)以上に「平成」を感じさせるものとなっていたと言わなければならない。あの頃、世界は確かに平ら(flat)に成っていたのである。
・荒木ゆう子「(scene)」展(2021.10.4〜16 gekilin.)

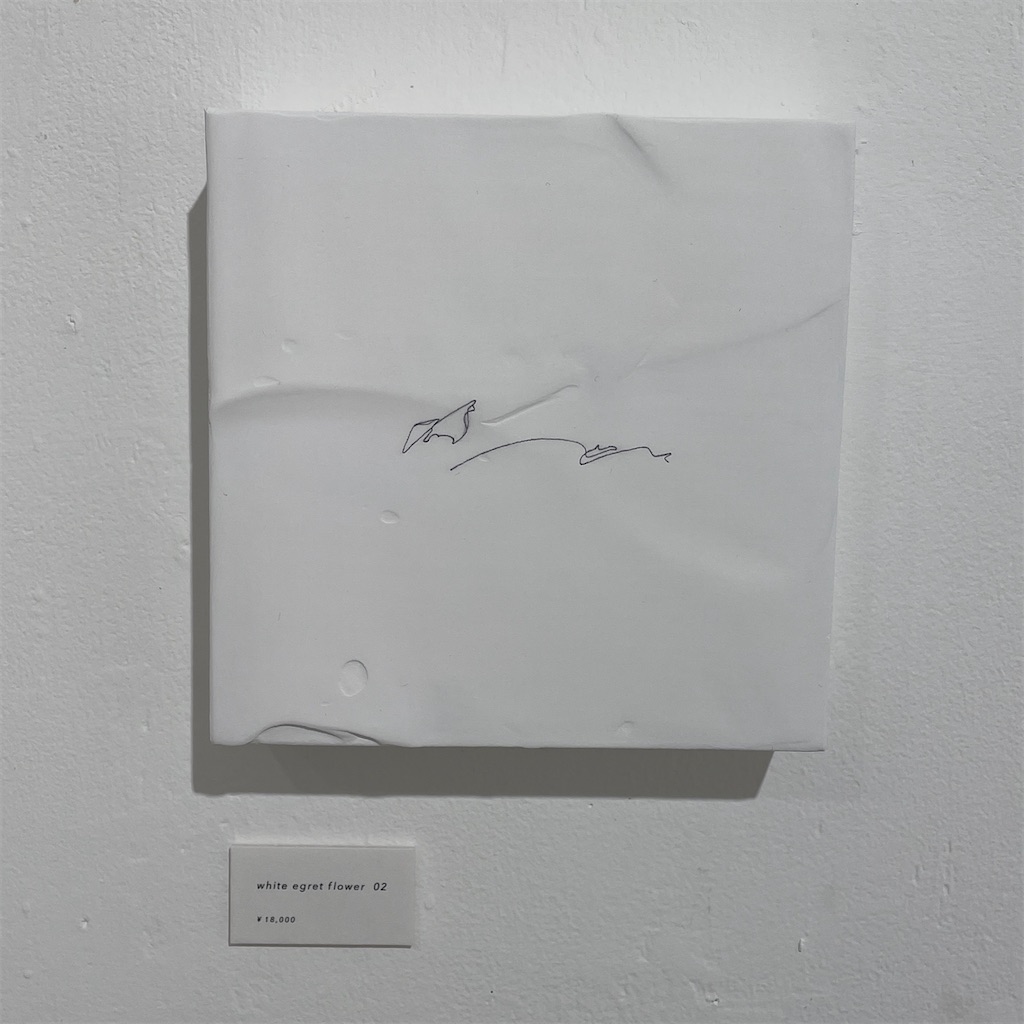
大阪で毎年開催されているUNKNOWN ASIAやグループ展などで着実にキャリアを積んできている様子の荒木ゆう子女史。この「(scene)」展はそんな彼女の初個展だったのだが、作品のクオリティやコンセプチュアルな精度が飛躍的に高まっていて瞠目。下地を作ったカンヴァスに鉛筆で花の輪郭線をドローイングしたあと、彼女自身が本当に必要だと感じた部分だけを残して作品とするという形で描かれていたのだが、その「本当に必要だと感じた部分」が、もはや元々何を描いていたのか一見して分からなくなるくらいまで省筆化されており、この大胆さには震撼しきり。実在の花から直観を頼りに〈(概念としての)花〉((C)世阿弥)を抽出しようとしているとも言える──実際、荒木女史は茶道を嗜んでいるという──のだが、ここまでくると、そういった(茶道・華道の文脈における)スピリチュアルなニュアンスが付与された〈花〉をも突き抜けた物質性・実在性を見る側に与えるものとなっていたわけで、初個展にしてここまでの達成を見せていたことに驚くばかり。
「フェミニズムズ」展+「ぎこちない会話への対応策 第三波フェミニズムの視点で」展


金沢21世紀美術館では2021.10.16〜2022.3.13の会期で〈フェミニズム〉をテーマにした二つの企画展「フェミニズムズ」展と「ぎこちない会話への対応策 第三波フェミニズムの視点で」展(以下「ぎこちない会話」展)が同時に開催されています。どちらもグループ展の体裁を取っており、とりわけ後者は1990年代にセルフポートレート写真を発表して一躍時の人となり、2020年に発売した著書『「僕ら」の「女の子写真」からわたしたちのガーリーフォトへ』(大福書林)で再び現代写真界隈に一石を投じた写真家の長島有里枝(1973〜)女史をゲストキュレーターに迎えている。かかる展覧会二本立てという構成を取ることで現代美術/現代アートとフェミニズムとの関係を、アート×フェミニズムというカップリングを視野に入れつつ、現時点においてより複眼的に(再)考察することが目指されていると、さしあたっては言えるでしょう。
○「フェミニズムズ」展出展作家青木千絵、遠藤麻衣、遠藤麻衣×百瀬文、風間サチコ、木村了子、森栄喜、西山美なコ、碓井ゆい、ユゥキユキ
○「ぎこちない会話への対応策 第三波フェミニズムの視点で」展出展作家岩根愛、木村友紀、小林耕平、さとうりさ、ミヨ・スティーブンス-ガンダーラ、長島有里枝、潘逸舟、藤岡亜弥、ミヤギフトシ、渡辺豪


《フェミニズムは1990年代以降、欧米の若い女性たちを中心にポピュラー文化と結びつき、メディアを通して広がっていきました。(中略)近年、フェミニズムは複数形で語られ始めました。世代や時代、所属する国家や民族、それぞれの環境や価値観によってフェミニズムの考え方や捉え方は異なります。複数形のフェミニズムが発するメッセージは、多様な考え方を認め合うことこそが社会にとって重要で必要だという視点です》──以上のような問題意識のもと、「フェミニズムズ」展ではゼロ年代〜2010年代に作家活動を始めた女性作家を中心にセレクトされています。その際「世代や時代、所属する国家や民族、それぞれの環境や価値観によってフェミニズムの考え方や捉え方は異なります」ということがひと目で即座に理解できるようなキャッチーな作品が多かったところに、この展覧会の独自性があると言えるでしょう。いくつか例をあげておきますと、青木千絵女史は漆芸で女性の身体を彷彿とさせる(が、全体的には不定型な)塊を作っていたし、木村了子女史はイケメンが躍動する様子を日本画として描いているし、ユゥキユキ女史は母親と編んだ毛糸を使って巨大なぬいぐるみ(中では二つの映像作品が上演されていた)を作っていたし、碓井ゆい女史は現在日本で使われている硬貨のデザインの中に今なお不可視化されている女性たちの労働を描きこんだ刺繍作品を出していたし、遠藤麻衣・百瀬文両女史は80分近い映像作品において二人で粘土をいじりながら「(男性/女性という対を決定的に逸脱する)来るべき性的生物」の可能性について語り合っていた。これらの作品に強く現われているように、「フェミニズムズ」展においては一見すると政治運動としてのフェミニズムから遠く離れているように見える作品が多く出ていたわけですが、しかしこれらの作品においては、より身近でありつつも、そうであるからこそ決定的な違和として彼女たちの前に現われたものごと──それは〈政治的〉なことというより、むしろ〈文化的〉かつセンシュアルでセンシティヴな領域におけるものごととして露呈する──を表現の出発点としている。かつて、というか今でも、政治・社会運動としてのフェミニズムは「個人的なことは政治的なことである」をスローガンとしていたものですが、ここにおいてはそのスローガンを軽くねじった「個人的なことは文化/政治的なことである」というべき態度が前面に押し出されているのでした。


かかる「ポピュラー文化と結びつき、メディアを通して広がってい」ったフェミニズム──それは現在においては(やや回顧的に)〈第三波フェミニズム〉と呼ばれ、「ぎこちない会話」展の方でよりヴィヴィッドに取り上げられることになるだろう(後述)──の象徴的存在として西山美なコ(1965〜)女史と彼女の作品が特権化されていることに注目する必要があるでしょう。「フェミニズムズ」展の出展作家中最年長であり、ただひとり1980年代から制作活動を続けている西山女史。金沢21世紀美術館では2010年に(当時「ニットの貴公子」というキャッチフレーズでテレビにしばしば出演していた)広瀬光治氏との二人展を開催しており、企画展への出展はそれ以来となっているようですが、今回は1990年代前半に大阪で開催した個展において行なったパフォーマンス&インスタレーションを、当時の素材を用いて再制作した作品が出展されています。このときの個展に際し西山女史は成人向け雑誌の広告欄に電話番号を掲載し、ピンクチラシやポケットティッシュも作るなどした上で会期中に擬似テレクラを開いていたという(今回は当時の実際の音声もスマホを介して聴くことができます(!))。西山女史といいますと、少女マンガに出てきそうなキャラクターや漫符、女の子向けおもちゃの外観などをモティーフにした平面やインスタレーション作品を同時期に作っており、近年は砂糖菓子でバラの花やティアラを作ったりピンクの壁画(たいていは会期終了後消される)を描いたりしていることで知られていますが、それらの作品において一貫しているのは、女性性、ひいては女性とは、キャラ、漫符、おもちゃ、砂糖菓子、バラ、ティアラ、ピンクチラシetcといった外的な諸事物のことであり、従ってその諸事物の表現の位相における関係性を変えることこそが(女性としての)自身の対自的な関係性を変えることであるという認識である。それを「典型的」であることや「過剰」であることを旨とする文化的な諸配置の中で生産された諸事物を使って、制作を通して遂行的に明らかにしているところに、彼女の作品の現在にも通ずる美質があるわけです。
以上のように、「フェミニズムズ」展では、1980〜90年代以降における〈第三波フェミニズム〉あるいはそれ以後におけるアートとフェミニズムの交差・交接が豊かな多様性と多産性を現在進行形で見せていることが主題となっていたのですが、かかる観点から見たとき、「ぎこちない会話」展はどのように位置づけることができるのか。上述したように、写真家の長島有里枝女史をゲストキュレーターに迎えているこの展覧会では、ある歴史性を刻印された概念としての〈第三波フェミニズム〉が「フェミニズムズ」展以上に大きな主題となっているわけですが、彼女において〈第三波フェミニズム〉はさしあたり以下のように定義されている。
第三波フェミニズム運動は、自らをフェミニストと名乗ることに戸惑いを持つ若い女性が多かったこと、表向きにはひとつの“運動”に見えなかったこと、文化的なアクティビティを通じて草の根的に繋がっていたことなどを特徴とし、「ガール」や「ビッチ」、「カント」などの女性蔑視的な言葉を自分に対して積極的に用いたり、女性らしい服装を自ら好んで身につけたりすることで、それらの持つネガティブな意味の解体を試みるなど、一見するとフェミニズムではなさそうな新しい手法をその実践に採用していた。また、あからさまな運動や政治活動の形態を取らずに、パンク・バンドとしての活動やスモール・パブリケーションの発行、アート製作などの方法でその運動が実践されたため、それがフェミニズム運動の一環であるという認識や合意が得られにくかったといえる。しかし、そのような運動の形態であったからこそ、一〇代や二〇代の若い女性たちに届きやすく、浸透しやすかったのではなかったか。(長島有里枝『「僕ら」の「女の子写真」からわたしたちのガーリーフォトへ』(大福書林、2020)、p371)
──長島女史において〈第三波フェミニズム〉とは、顕在化・可視化されない(「表向きにはひとつの“運動”に見えなかった」)が、潜在的には非-存在していた(「文化的なアクティビティを通じて草の根的に繋がっていた」)、言うなればムーヴメントならざるムーヴメントであったとされているのですが、そのような性格を持った動きを参照項としているこの「ぎこちない会話」展では、女性のみならず男性も出展作家に含まれており、その点において「フェミニズムズ」展と著しい対照をなしています。このことから見えてくるのは、「ぎこちない会話」展においては、この間の女性美術家による表現の多様性以上に、その多様性のアクチュアリティを担保して外的な諸構造・諸現実へと紐付ける一種のメタ言語(お好みなら「美術批評」と言い換えてもいいでしょう)が主題となっているということである。そう言えば『「僕ら」の「女の子写真」からわたしたちのガーリーフォトへ』も、まさに自分自身を輩出した1990年代の写真界における、メタ言語としての写真批評において横行したジェンダーバイアスによる偏った理解というか誤解──その象徴的なキーワードとしての「女の子写真」の提唱者であった写真評論家の飯沢耕太郎氏への批判が、同書における重要なモーメントとなるだろう──が、彼女自身や同時期にデビューした女性写真家(HIROMIXや蜷川実花など)をめぐる言説全般に見られた現象であったことに一貫してフォーカスが当てられていたのでした。従ってこの展覧会では個々の作品以上に、それらに通底する/それらを通底させる言説=アート/フェミニズムという対質の歴史性へとピントを合わせることが観者に要請されることになる(が、その手引きとなるはずの図録や記録集、論考集が発売されていなかったのは、いささかマズいのではないか(←追記:図録の発売が予定されているそうです))。
ところで長島女史が上の引用文において「自らをフェミニストと名乗ることに戸惑いを持つ若い女性が多かった」「一見するとフェミニズムではなさそうな新しい手法」「あからさまな運動や政治活動の形態を取らずに」など、否定形を用いて〈第三波フェミニズム〉を語っていることは、きわめて徴候的であると考えられます。ここには日本における〈第三波フェミニズム〉が、それ以前の第一波・第二波フェミニズムからの発展として展開されたのではなく、むしろそれらと逆立する形で展開されていったことが遂行的に示されている。日本の場合、1960年代末からの第二波フェミニズム=ウーマン・リブ運動が連合赤軍事件──ウーマン・リブ運動の近傍にいたとおぼしき永田洋子(1945〜2011)が連合赤軍内で支配権を確立し、総括と称して女性メンバーも殺害した事件──に帰結したという歴史があるわけで、そのことが〈第三波フェミニズム〉の中で登場した世代をも強く規定し、独特の圏域を形成していったことは想像に難くない。実際、この事件(とその後における新旧問わない左翼諸党派によるいわゆる「内ゲバ」)は社会運動や政治活動への忌避感情の根拠として今日に至るまで日本の文化/政治の基礎をなしているわけですが、長島女史のかような語りもまた、そのような圏域の所在を裏側から指し示していると言えるでしょう。
いずれにしても「フェミニズムズ」展においては多様性と同時多発性に、「ぎこちない会話」展においてはそれらの基盤となる運動論における歴史性にフォーカスすることによって、欧米の諸動向のカーボンコピーではない、日本のフェミニズムへと観者を使嗾させるものとなっていたところに、二つの展覧会の特筆大書すべきアクチュアリティがあったと言えるでしょう。まだ十分ではないところもあるとはいえ、別の美術史、別のアート/フェミニズム史への決定的な一歩が踏み出されたことを、まずは言祝ぎたいところです。